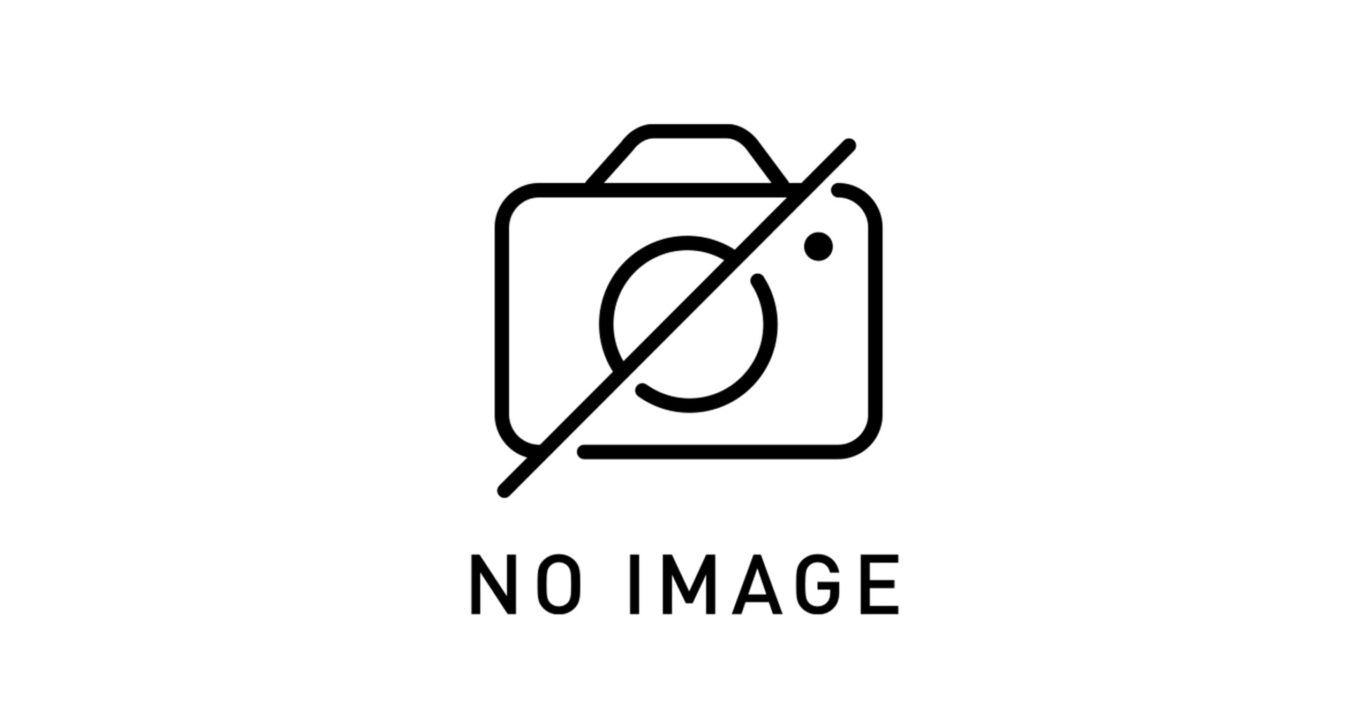御香宮神社
ごこうのみやじんじゃ
| 住所 | 〒612-8039 京都府京都市伏見区御香宮門前町174 |
| 電話番号 | 075-611-0559 |
| FAX | |
| HP | https://www.gokounomiya.kyoto.jp |
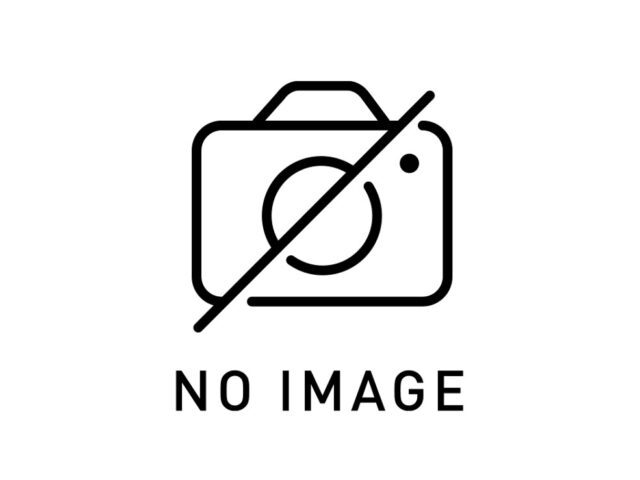
由緒・由来
当社は通称「ごこんさん」として古くより地域の人々から親しみをもって呼ばれ、旧伏見町一帯の氏神として信仰を集めている。創建時は不詳であるが、御香宮縁起(三巻)によれば、貞観4年(862)9月9日御諸神社境内より「香」のよい水が湧出する奇瑞により、御香宮の名を清和天皇より賜ったとされている。しかし香椎宮編年記(香椎宮蔵)によれば弘仁14年(823)御祭神神功皇后の神託により、この地に宮殿を修造し椎を植えて神木としたと伝えられている。
室町時代、当社は伏見九郷の荘民等の「一庄同心」という精神的な支えの中心となっていた。天正18年(1590)小田原の北條氏を滅亡させ、天下統一を遂げた豊臣秀吉は、当社に戦勝祈願をなし、太刀(重要文化財)と願文を納め社領三百石を寄進した。文禄3年(1594)秀吉は伏見築城に際して城の鬼門除けの神として城内の艮の隅に勧請した。慶長10年(1605)徳川家康は再び社地を元の地に復し、本殿を造営し秀吉にならって社領三百石を寄進した。元和8年(1622)伏見廃城に先立って、水戸徳川家の初代徳川頼房が伏見城の大手門を拝領、それを当社の表門として寄進した。寛永2年(1625)には、都名所図絵巻五に
御香宮(略)「拝殿南のもん」彫刻等華美なり、伏見の城中にありしをここにうつす
として紹介されている拝殿を紀州徳川家の初代徳川頼宣が建立されたと伝えられている。慶応4年(1868)正月、鳥羽伏見の戦いの際には伏見奉行所に旧幕府軍が拠り、当社は新政府軍(薩摩藩)の屯所となったが、幸にして戦火は免れた。
10月上旬に行われる神幸祭は、伏見九郷の総鎮守の例祭とされ、古来『伏見祭』と称せられ、今も洛南随一の大祭として評判を得ている。
※御香宮神社様HP 神社由緒より